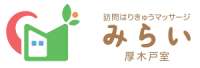パーキンソン病とは
パーキンソン病は進行性疾患であり、運動系の障害として振戦、筋固縮、無動、姿勢反射障害(4大徴候)があります。
精神系の障害としては抑うつ、認知機能障害、幻覚、妄想、REM睡眠行動障害がみられます。
自律神経系の障害としては便秘、起立性低血圧、排尿障害、脂漏、性機能障害、嚥下障害などがみられます。
睡眠障害としては不眠、悪夢、覚醒リズム障害などがあり、感覚障害も痛みや嗅覚障害も生じます。
進行期になると上記の多彩な障害が出現し、リハビリテーションやケアの大きな課題となります。
発症は、20~80歳代までの報告がありますが、好発年齢は50~60歳です。40歳未満の発症は若年性パーキンソニズムと呼ばれています。
有病率は人口10万人に対し約100~150人と神経疾患の中でも有病率が高くなっています。
パーキンソン病と付き合っていく生活
パーキンソン病罹患の患者様の平均寿命は一般平均と差がなく、天寿を全うできる疾患です。
発症初期は運動系の障害はほとんどなく、腰痛やうつ傾向で整形外科や精神神経科を受診している例も少なくありません。
進行のスピードは個人差がありますが、長期にわたって治療、リハビリテーション、ケアが必要となります。
具体的に治療は、薬物療法とリハビリテーションがメインになります。
病状が進行すると、長期薬物投与による副作用や運動障害の進行に加え、認知機能や精神機能の障害により、在宅生活が困難となりやすく、医療機関入院(医療保険分野)、老人ホーム・高齢者施設などの施設入所(介護保険分野)を繰り返しながらの在宅生活となります。
お薬やリハビリなど適切な治療を続けることで毎日の生活が送りやすくなりますが、長い療養生活の間に、患者さんとご家族が負担に感じることもあるかもしれません。
在宅生活では閉じこもりになりやすいため、通所介護、訪問リハビリ等によるさまざまな活動やサービスを利用することで負担を軽減することができる可能性があります。
また、ほかの神経難病と比較すると、全国パーキンソン病友の会をはじめ各地域で本人・家族を支援する会やネットワークが整っており、これらを活用することで精神的な負担軽減にもつながる可能性があります。
リハビリの重要性
リハビリは、薬物療法と並ぶパーキンソン病の治療の重要な柱です。
なかでも運動は、神経の働き改善と血行促通により、神経回路の流れがスムーズになる効果を期待でき、心身機能維持・向上、姿勢や歩行の障害、認知機能低下、気分の落ち込み、日中の眠気など、さまざまな症状の改善につながる可能性があります。
リハビリは、日常生活に支障が生じていない時期から始めることが重要です。主治医の指示にしたがって、ストレッチ、ウォーキング、筋力トレーニングなどをなるべく早い時期から始めましょう。リハビリで大切なのは継続です。運動を生活の一部にすることです。
患者さんご本人では運動をすることが難しい場合は、周りの人にサポートしてもらいながら行いましょう。
また、ご家族も一緒に楽しく行うことがリハビリの充実や継続につながります。
安全に歩くための工夫
パーキンソン病の患者さんは、知らないうちに動作が小さくなっています。ご自身が普通と感じているよりも大きく動かすことを心がけましょう。
すくみ足になってしまった場合は、その場で足踏みをしたり、足をあえて後ろに引くとスムーズに前へ歩行できることもあります。
また、突進し始めてしまっても、慌てずその場で止まり、姿勢を整えて深呼吸してから、ゆっくり大きく歩き出しましょう。
またパーキンソン病の進行とともに転びやすくなるため、転倒予防は重要です。体を動かす際はあせらず、ゆっくり、集中することを常に意識しましょう。
方向転換をするときも転倒しやすいため、十分に注意する必要があります。
生活の工夫:食事の工夫
パーキンソン病に多く見られる便秘への対策として、食物繊維の多い食品(海藻、さつまいも、バナナなど)に加えて、乳酸菌を含む食品(ヨーグルト、ぬか漬け、キムチなど)も摂りましょう。
また、食べ物がうまく飲み込めない嚥下障害が生じた場合は、とろみをつける、やわらかくする、すりつぶすなどの工夫で飲み込みやすくなります。
パーキンソン病とご家族
パーキンソン病患者さんがより豊かな人生を歩んでいくためには、患者さんご本人の前向きな気持ちと、それを支える周囲のチームワークが不可欠です。
ご家族は、患者さんの気持ちや体の状態をよく把握し、励ますことができる存在であり、医療チームの一員です。
患者さんは将来への不安などから気分が落ち込みがちです。不安を聞いてもらうだけでも気分が和らぎます。患者さんが前向きになれるように支援していきましょう。
そして、支援が必要なのは患者さんだけではありません。ご家族もまた支援が必要な時があるでしょう。
ときには周りの人やさまざまなサービスを利用し、助けを求めることも大切です。