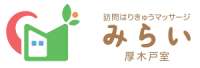変形性膝関節症とは
変形性膝関節症は、痛みや歩きにくさなど生活で困ったことが多くなる病気です。膝の軟骨が減少して、変形したり骨がこすれて、痛みが起きる病気と言われています。症状としては、膝の痛みや膝が腫れる(水がたまる)、こわばりなどが生じます。症状の進行でみていくと、発症初期には立ち上がり、歩き初めなど動き初めのみの痛み。中期には正座や階段昇降が難しくなる。末期には安静時でも痛い、関節の変化が目立つ、膝が伸びにくい、歩くのが難しくなるなどの症状が出ます。
大規模な研究によると、日本における変形性膝関節症の患者数は約2500万人と推定されており、変形性膝関節症に苦しんでいる方は多いです。症状が出る変形性膝関節症の発症率は1.6~9.4%、特に高齢者で10~15%とされており、年齢と強く関係していると言われています。また女性の発症率が高いことも知られています。
変形性膝関節症にかかる可能性を高める危険因子というものがあります。全身的な因子は、年齢、性別、民族、遺伝、代謝が挙げられます。局所的な因子は、筋力低下、感覚低下、膝の動揺性、受傷、負担増、肥満が挙げられます。
膝が痛む原因
変形性膝関節症の痛みの部位とそのメカニズムについては十分な解明は得られていないと言われています。レントゲン上、膝に変形があったとしても7~8の方は痛みが生じないと言われており、必ずしも変形が痛みとイコールではありません。膝関節周囲には痛みを出す組織がたくさんあります。筋肉や半月板、脂肪、滑液包(ゼリー状でクッションの役目をする)、靭帯など様々あります。膝が変形していく際に、軟骨の摩耗した粉が関節を取り囲む関節包という関節の袋に作用し、膝関節内に炎症が生じます。その炎症によって、膝関節周囲の筋肉や脂肪が硬くなることがあります。その状態で歩行や階段昇降などによって、二次的にこれらの硬くなった組織に負荷がかかることで痛みが発生します。
変形性膝関節症の治療
大きく分けて2つあり、手術療法と保存療法があります。手術療法は、人工膝関節置換術や高位脛骨骨切り術、関節鏡手術などがあります。保存療法は、薬物療法や装具療法、理学療法(リハビリ)があります。今回は保存療法を主に説明していきます。
変形性膝関節の保存療法
薬物療法では鎮痛剤や関節内注射を行うことで、痛みの緩和を図り関節の動きを良くします。装具療法では、足底板や膝関節装具(サポーターなど)により、関節を安定させたり、足の向きを変えることで痛みの緩和を図ります。理学療法(リハビリ)では、運動療法や徒手療法、物理療法、生活指導により痛みの緩和を図ります。病院やクリニックでは、医療保険を用い、医師の診断のもとリハビリを受ける事ができます。また介護保険をお持ちの方は、デイケアや訪問リハビリによりリハビリを受ける事ができます。訪問リハビリでは、自宅内での動きに問題を抱えている方や悩みがある方には最適で、自宅の環境に合わせたリハビリ・生活指導を受けることができます。
自主訓練で変形性膝関節症の痛みを軽減する
病院でのリハビリや介護保険サービスを利用することで、膝痛軽減につながる可能性はあり、有効な手段です。しかし、1日24時間、1週間168時間の中でリハビリを受ける事ができる時間はわずか数十分程と思います。
また、その時はリハビリにより一時的に疼痛軽減しても、翌日には痛みがもとに戻っていることも多いと思います。そのため、リハビリに通われている方は、効果を持続する目的、通われていない方は痛みを軽減する目的で自分で行えるストレッチや運動を行い、筋肉の緊張をコントロールしたり、筋肉を強くすることが必要です。
ストレッチの効果・注意点
ストレッチを行うことで、筋肉や腱が伸び、筋肉の柔軟性が高まります。また血行促進、疲労回復効果もあります。ゆっくりと呼吸を止めずに無理のない範囲で行うことが大切です。痛みを感じるほどの強さでストレッチを行うと筋肉が緊張してしまうため逆効果となります。膝痛には特にふくらはぎ(下腿三頭筋)や太ももの裏(ハムストリングス)を伸ばすストレッチが有効です。
生活の工夫
変形性膝関節症により痛みがあってもなくても、生活の工夫により症状の進行が抑えられる効果が期待できます。
・歩き初めは少し足踏みをして、急に歩き出さない
・痛みがある側と反対の手に杖をもつ
・階段昇降の昇りは痛くない足を先に、降りは痛い方を先に出すことで膝への負担が軽減します。
・無理やり正座など膝を深く曲げるような姿勢を取ると痛みが強くなる可能性があります。
・しゃがむ際や床から立ち上がる際は何かものに掴まるか、片膝をつきながら行うとよいです。
・万歩計や携帯電話の歩数計を利用して、一日の歩行量を記録しましょう。歩行量と痛みの関係性が分かるかもしれません。自分にあった歩数をみつけましょう。
・体重増加は膝への負担を大きくし、痛みを強くする可能性があります。エルゴメーターや水中ウォーキングなど膝への負担が少ない運動を行い、体重を減らしましょう。