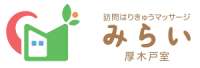高齢者に多い腰痛
高齢者は腰痛の訴えが多く、病院や整骨院に通われている方も多いと思います。
整形外科疾患では発症日から150日しか病院でのリハビリテーションを受けることができず、長期化する腰痛にたいしては医療保険で対応できないこともあります。
特に腰部脊柱管狭窄症と腰椎圧迫骨折は痛みが長期化することが多いことから医療保険で対応できる期間を超えても痛みが残存することが問題となっています。
今回はそれぞれの原因と対処法について解説します。
腰部脊柱管狭窄症とは
椎体といわれる背中を支えている骨から神経が伸びていますが、神経が出てくる穴である椎間孔が狭くなることで様々な痛みや神経症状を引き起こすのが腰部脊柱管狭窄症です。
特徴的な症状としては、数分歩くと足に痛みや痺れが生じ動けなくなるが、休んで時間が経過するとまた動けるようになる「間欠性跛行」が特徴的な症状です。
脊柱管の狭窄程度によりますが、一般的に腰を反らしたり捻ったりすることで症状が生じることが多く「間欠性跛行」と「伸展時の腰部・下肢痛」が生じるひとは整形外科への受診をおすすめします。
腰部脊柱管狭窄症の対処法
腰部脊柱管狭窄症では、一般的にリハビリテーションによる保存療法と狭くなった椎間孔を広げる手術の2つの対応がとられます。
ただし、手術をしなくてはならないような状態は、耐え難い痛みが続いていることや排便排尿障害といった排泄に支障が生じるような重篤な状態で手術が勧められることが多いです。
通常はリハビリテーションによる保存療法がとられます。
リハビリテーションでは初期に痛みの緩和が中心ですが、痛みや痺れの緩和後には椎間孔が狭くなる原因に対しての治療が必要となります。
よくあるパターンでは股関節の前面が過剰に硬く、股関節の伸展動作が上手く生じないことで歩くときに腰への負担が大きくなっているパターンや脊柱の可動性が低下していることで腰椎が過剰に反りすぎてしまうパターンがあります。
どちらにせよ股関節や脊柱のストレッチが必要となります。前述したとおり発症後150日以内では医療保険を使って病院でのリハビリをおこなえますが、それ以降では保険が適応されなくなるケースもあるため、介護保険の認定を受けている方は介護保険を利用して、デイケア、リハビリテーション特化型デイサービス、訪問リハビリなどのサービスを利用して改善を目指すことになります。
腰椎圧迫骨折とは
腰椎圧迫骨折とは高齢者が転倒などでしりもちをついたときに受傷することが多く、椎体と呼ばれる背骨の中で体重を支える部分がつぶれるように骨折した状態です。
しかし、骨粗鬆症を発症している人ではしりもちなどの衝撃がなくとも「いつの間にか骨折」と呼ばれるように明確な受傷機転なく、最近腰が痛いと思っていて病院受診したときに発覚することもあります。
特に女性は閉経後にホルモンの影響により骨粗鬆症を発症しやすいといわれており、特に閉経後10年~15年の間に危険性が高くなります。
また、骨粗鬆症を併発した腰椎圧迫骨折ではその後も隣接する箇所の骨折を生じやすいといわれており、骨折を繰り返さないためにも受傷直後からのリハビリテーションとその後の対応が非常に重要となります。
腰椎圧迫骨折の対処法
受傷機転が明確な腰椎圧迫骨折を予防するためには、転倒しない足腰作りが重要となります。
特に60代からは急激に下肢の筋力が低下しやすいといわれているため、習慣的な運動が必要となります。
骨折してしまった後のリハビリテーションでは初期に痛みの緩和のために安楽肢位といわれる痛みが少ない姿勢の指導と痛みが生じない範囲での下肢運動や腹筋をおこないます。
痛みの緩和後には転倒予防のために下肢筋力トレーニングと骨折部位への負担を減らすための腹筋運動を中心におこないます。
腰痛を予防するには
高齢者に多い腰部疾患である、腰部脊柱管狭窄症と腰椎圧迫骨折を予防するためには習慣的に運動する必要があります。
特に体幹や下肢の筋力は転倒予防や腰椎への負担を減らすために重要な筋力です。
現在は新型コロナウイルスの影響で、外出自粛を呼びかけられています。
訪問リハビリ等の訪問サービスを利用することで自宅にあるものを使った筋力トレーニングを指導してもらうことができます。
また、腰痛発症後には運動療法を中心とするリハビリをおこないますが、医療保険には期限があるため再発予防の運動やストレッチが重要となります。
特に股関節と脊柱の関節可動域の拡大と体幹・下肢の筋力トレーニングが必須です。
自分で管理できる人は問題ありませんが、運動習慣がない人や自分1人での運動に不安がある人は身体の専門家のサポートを受けることをおすすめします。