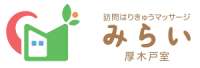腰痛とは
腰痛とは、その痛みの程度は差はあるもののほとんどの人が感じる症状の1つといわれています。
「病気とは」捉えず、「単に調子が悪い状態」と説明される事さえあります。
腰痛の調査から、腰痛の生涯有病率は60~80%の高率であり、どの時点でも20~30%に腰痛を認めると報告されています。
また、8~12週で80~85%が自然寛解するが、60%は再発するとも報告されています。
わが国の厚生労働省が実施した2007年の国民平均基礎調査の通院率をみると、腰痛症は高血圧に続いて女性では2位、男性では4位と高い罹患率が示されています。
腰のしくみ
人の背骨(脊柱)は、頚椎7個、胸椎12個、腰椎5個、仙椎5個、尾骨3~6個がつながって建物でいう大黒柱を作っています。つまり仙椎は骨盤とともに基礎をつくり、腰椎は1階部分を、胸椎は2階部分を頚椎は3階部分を支え、それぞれの機能・働きによりあった形状をしています。
腰椎がこれらのうちで最も大きな椎体(脊椎の前方部分の名称)を持ち、後方の突起も一番よく発達しています。
これは体重を多く支えるため、多くかかるストレス(負荷)に耐えられるように発達した形をしています。
「腰が強い」「腰を据える」「ねばり腰」などの表現は安定性を、反対に「腰がすわらない」とは不安定なことの表現です。このように日常的なイメージからも、実際の形からも「腰」は「安定」という機能・働きがあり、腰椎の最大の特徴です。
また、椎体の後方には孔があいています。これは脊柱管と呼ばれ、脳から下行してくる脊髄神経を入れ、保護をしています。
この脊柱管の大きさは頸部と腰部で大きいのですが、椎体の大きさほどはっきりした差はありません。
腰椎の神経保護は、頚椎、胸椎と同程度にもう1つの大切な役割なのです。
つまり、腰椎の役割のうち安定性に支障が起これば、腰痛、神経保護に障害が発生すれば神経痛として症状が現れます。
椎体の役割
脊椎の前方部分を椎体といいます。高さの低いほぼ楕円柱の骨の塊が連なっており、腰にかかる負荷を一番多く受け止めます。つまり腰の安定性の基本が椎体です。
椎体はカルシウムの貯蔵庫としての役割もあり、骨粗鬆症の影響を人体の中で一番多く受けます。
さらに血液の生産センターの役割も担っていて重要な部分なのですが、骨粗鬆症による骨折や癌の転移が起こりやすい部位でもあります。
骨粗鬆症と腰椎圧迫骨折
腰椎圧迫骨折の典型的なものは骨粗鬆症のある高齢者がしりもちをついて受傷することです。
また原因がわからず(身に覚えがなく)腰痛を主訴に医師を受診したら腰椎圧迫骨折と診断されることは多くあります。
この腰椎圧迫骨折では、腰椎の椎体が骨折します。男女比の割合では圧倒的に女性が多いです。
一般に骨のカルシウム量は30歳代でピークになり、以降年齢とともに減少します。
日本人の女性は40歳頃から急激に骨量の減少をきたし、特に閉経前後10~15年の間に急激な減少が起きます。
70歳頃になると、高齢者特有の骨折を起こす割合が増加していきます。
圧迫骨折の治療
急性期(痛みの激しい時期)には、ベッドで一番楽な姿勢で寝て、できる限り安静を保つようにします。
2週間以内でだいたい痛みが緩和し、楽になります。多くの高齢者の方は、寝込むと二度と歩けなくなる、いわゆる「寝たきり」になるのではと心配され、少し良くなると動こうとされます。
しかし、注意しないと激しい痛みに襲われて結局痛みが長引きます。
この寝ている間も、腹筋や足の筋肉を鍛える運動はベッドでできるので、それを実行することで筋力低下を予防し、痛みが緩和した後歩けるようになるまでの準備ができます。
痛みがなくなった後も、圧迫骨折をはじめとする高齢者に多い骨折の原因となる骨粗鬆症の治療は必要です。
服薬だけでなく、運動をすることで骨量を増やすことが期待できます。
また、高齢者の中でも特に転倒して骨折した方は、転倒予防に配慮する必要があります。
退院してからが生活のはじまり
圧迫骨折をすると病院に入院することが多く、いずれは退院する必要があります。高齢者の方が多いため、退院先は自宅だけでなく、老人ホームになることもあります。
自宅に退院となっても生活に不安がある方は介護保険を利用し、サービスを受ける事が可能です(介護保険申請が必要です)。
訪問リハビリでは、自宅環境に合わせた転倒予防の練習ができ、自宅での生活をより安全に送れるサポートができます。
デイサービス・デイケア、老人ホームなどでは、レクリエーションや機能訓練、体操を通して、全身的な運動、転倒予防の運動を行うことができ、再骨折の予防が期待できます。
介護保険や施設入所し、介護保険のサービスを利用されない方も日々のウォーキングや運動が筋力低下の予防、骨量低下の予防につながり、継続することが大切です。
また、筋肉性の痛みがある場合などは、訪問マッサージを利用することで痛みが緩和する可能性もあります。
加えて重いものを持つ、長時間同じ姿勢を取る、腰をたくさん曲げる等は腰痛つながる可能性があり、注意しながら生活を送りましょう。