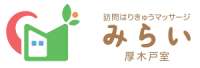対策キーワード:介護保険、訪問リハビリ、福祉施設、高齢者施設、老人ホーム
サブキーワード:パーキンソン病、リハビリ、関節可動域の拡大、機能訓練、ストレッチ、筋力低下、自律神経
パーキンソン病と重症度分類
パーキンソン病は脳に異常が起き、体の動かしづらさや自律神経系の症状が出現するなど様々な症状を呈する進行性疾患です。
病気の進行程度により、ホーンヤールの重症度分類というもので5つに分類されます。
ステージⅠでは、筋肉のこわばりやふるえなどの症状が片方の手足に現れます。
ステージⅡでは、筋肉のこわばりやふるえなどの症状が両方の手足に現れます。
ステージⅢでは、姿勢反射障害という姿勢を保つバランスが保てなくなり、やや活動が制限されます。
ステージⅣでは、歩くことや立つことがかろうじて可能ですが日常生活の一部に介助が必要となります。
ステージⅤでは、歩くことや立つことが困難となり、日常生活の大部分に介助が必要となります。
パーキンソン病患者さんの在宅生活
パーキンソン病患者さんの在宅生活がどのようになっているかを考える前に、健常者はどのように生活しているのか総務省のデータを参考に見ていきます。
総務省では、全国8万世帯、約20万人を対象に調査を実施し、一般的な国民の生活行為の内容と費やしている時間を詳細に調査しています。
基本調査では生活行為を1次活動(生理的活動:睡眠・身の周りの用事・食事)、2次活動(役割活動:家事や仕事など)、3次活動(余暇活動:趣味や休息など)に大きく3つ分類しています。
この調査の結果、1次活動に費やす時間は、起床から就寝までの時間の約20%前後でした。また1次活動の割合は一生を通じて大きな変化がないこともわかりました。2次活動、3次活動の領域は、いわゆる「その人らしさ」に相当する部分で、就職や定年などライフイベントを機に大きく変化します。
訪問リハビリで関わった在宅パーキンソン病患者さんの生活を、各活動の割合を重症度ごと(ホーン・ヤールの重症度分類)に同様の方法で調査した報告があります。
1次活動では、重症度に関わらず、基本調査(総務省の調査)と統計的に差は認められませんでした。
2次活動では、ステージⅡ以下で極端に短くなっています。
3次活動ではステージⅢ、Ⅳで基本調査より統計的に長くなっていました。また3次活動の内容を調べてみると、ほとんどがテレビ視聴やボーっとしているなど、消極的な時間で占められていました。
役割が消失し、受動的な生活を送っている在宅パーキンソン病患者さんの生活構造がわかります。
パーキンソン病の進行に伴う各ステージでの目標
ステージⅠ・Ⅱの段階では、自分で身の周りのことをできることが多く、自宅での生活を送ることが可能です。
またウォーキングや筋力トレーニング、医療機関でのリハビリ(ストレッチ・関節可動域の拡大、機能訓練等)、福祉施設での転倒予防教室等、様々な活動を通して積極的に運動することができます。
この時期の目標は、家事や仕事をしている方は、できるだけ継続して行い、周りの人たちは支援することです。
さらに外出などに関連する化粧や整髪等を含む整容、更衣の工夫を行い時間の短縮を図ることも大切です。
ステージⅢ・Ⅳの段階では、介護保険を利用し、ヘルパーやデイサービス・デイケアの利用、必要な方は高齢者施設や老人ホームへ入所することがあります。
この時期は、排泄・食事・入浴などへのサービス等での介入とともに2次活動の消失を防ぎ、消極的3次活動を積極的3次活動に変えることを目標とします。
ステージⅤでは、多くの方が医療機関への入院、高齢者施設への入所を行い、介護・看護を必要としながら生活することとなります。
この時期の目標は、特に食事に関する介護負担をできるだけ減らし、生理的活動の割合がほかの活動を上回らないようにすることが大切です。
これら各ステージでの目標は、患者さんご自身・ご家族や看護師・介護士・リハビリ職様々な視点からみた共通の目標になります。
自宅環境の工夫
自宅で安全に生活するためには、自宅環境や道具を利用することも大切になってきます。
すくみ足・小刻み歩行が出やすい方は、ベッドやトイレ、よく使う椅子の前に目印となるテープなどでマーキングすることですくみ足を予防することができます。
それでもすくみ足や小刻み歩行になる方は、膝から転倒して床に膝を付けることが多いため、膝にサポーターをして、骨折や打撲の予防をすることができます。
また、テレビや扇風機などのコード類は、動線にかからないように固定するとよいでしょう。
薬を飲み忘れて、気づかぬうちに症状が悪化することもあります。服薬時間別に分類した箱や服薬用のカレンダーなどを利用して整理することで、飲み忘れを防ぐことにつながります。ステージが進行し、症状が悪化してくると全身的な筋力低下も生じます。
布団が重くなることで寝返りが難しくなったり、起き上がる際の負担になる可能性があります。できる限り軽いものにすることも大切です。
長く付き合っていく進行性の疾患であるからこそ、さまざまなサービスや工夫が重要であり、これらは少しでも生活をより豊かにできる可能性を秘めているでしょう。